

7月には参議院選挙が予定されており、全国で若者の投票を促す啓発活動が活発になっている。選挙のたびに「若者の投票率の低さ」が指摘されるが、果たして若者の関心や責任感の問題として片づけてよいのだろうか。
多くの国で若者の政治的無関心が課題とされる中、スウェーデンの若者たちは全く異なる風景をつくり出している。たとえば、2018年の総選挙では18歳〜29歳の投票率が85.0%に達し、全体とほとんど変わらない。一方、日本の同世代の投票率は35〜40%前後で、2倍以上の差がある。政党参加率でもスウェーデンは若者の9.6%が政党に所属する。日本の約7倍にあたる。また30歳以下の国会議員も多く、過去には18歳で当選した例もある。若者が日常的にデモや請願で社会に意見を表明することも、決して特別ではない。気候変動ストライキを始めたグレタ・トゥンベリさんもスウェーデン出身であり、世界中の若者たちに影響を与えた。
この違いは、若者の意識だけでなく、声を聴き、関与を支える制度や文化の違いにある。背景には若者を「社会の構成主体」と捉える若者政策と、それを支える「ユースワーク」の実践がある。ユースワークとは、若者の居場所をつくり、若者の自己決定と社会との接続を支援する実践である。多くのヨーロッパの国では制度の一部として整備され、地域には若者の居場所として「ユースセンター」が設置されている。日本でも、こども家庭庁が「子ども・若者の意見を施策に反映する仕組みの整備」を全国の自治体に義務づけており、若者参画は制度上も本格的に求められている。
さらに、若者の参画は、社会の民主性を高めるだけでなく、個人の幸福感にも寄与する。神戸大学の西村和雄氏と八木匡氏による研究によれば、人生の節目で自分の意思で進路や就職を決めた人ほど、主観的幸福度が高く、他者への信頼や寛容性も高い傾向があるという。
制度を整えるだけでなく、日常の中で「声を出せる居場所」と「参画の機会」をどう確保するかが問われている。その両方を支えるのがユースワークだ。参画の習慣は、一朝一夕では育たない。若者が「声を出し、届ける」ことを日常にできる社会こそ、持続可能な民主主義の礎となるのではないか。
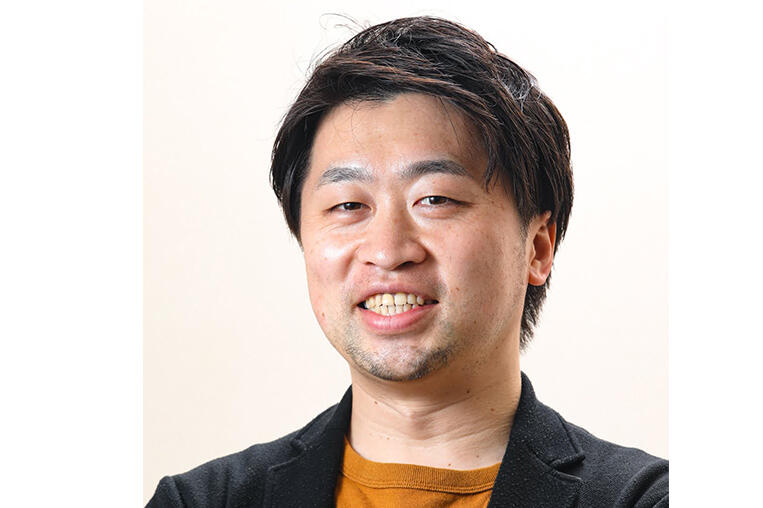
両角達平 社会福祉学部講師
※この原稿は、中部経済新聞オピニオン「オープンカレッジ」(2025年6月19日)欄に掲載されたものです。学校法人日本福祉大学学園広報室が一部加筆・訂正のうえ、掲載しています。このサイトに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。